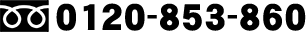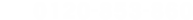2013年10月1日
塚本智也展 「不在」を描く
自分が「存在」について考えるきっかけとなった作品に、高松次郎の《影》があります。美術館で赤ん坊の影の絵を始めて見た時、実体のない影を絵にすることに感銘を受けました。

高松次郎(1936年~1998年)
1958年に読売アンデパンダン展に初出品し、60年代に瀬川原平、中西夏之と「ハイレッド・センター」を結成。《影》シリーズは60年代前半より制作され、60年代後半〜70年代にかけて起こった「もの派」の運動に影響を与えたと言われ、高松次郎は「プレもの派」と位置される。《影》は当初から作者自身の見解を超え、様々に語られてきた作品。「もの派」理論の支柱であった李禹煥は、高松自身の実在しないものを作るという「不在性説」を退け、著書『出会いを求めて』の高松次郎論のなかで別の見解を述べている。「意識」より「身体」で感じることに重点を置いていた李は、「視覚と実在のズレ」を身体的に知覚させる作品として高く評価した。また批評家・中原佑介に「画面に描かれた影とそれを見る鑑賞者の影とが混じり合って区別がつかなくなる点に特徴があり」、「画面のこちら側すなわち現実世界にイリュージョンを発生させる」と評され、「鑑賞者の身体」にも影響を与える作品でもある。一方で高松次郎があくまで「プレもの派」と位置づけられるのは、「ものではなく形にこだわり続けた」ことにあり、「身体への問いと形へのこだわりの分裂の中」という「もの派」とはまた別の次元のうちにいたのではないかとされる。
最近のブログ
月別アーカイブ
- 2026年
- 2026年1月 (5)
- 2025年
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (9)
- 2025年10月 (18)
- 2025年9月 (30)
- 2025年8月 (11)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (7)
- 2025年5月 (69)
- 2025年4月 (41)
- 2025年3月 (10)
- 2025年2月 (17)
- 2025年1月 (27)