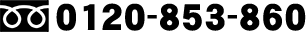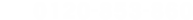2018年3月20日
白井晟一の書 得心
白井晟一の書
得心

書をする人の中には書いていく途中で、自分の字をデザインし、作っていく人もいるようだが、私にはそれができない。筆をおとしたら、それっきりである。
紙を突き抜けるように一気に書く。
日本の紙は、この筆力を支えきれずに破けてしまうし、筆も1週間に一本つぶしてしてしまう。
硯も筆も選ばぬが、その為紙は、中国の紙、玉版箋、筆は硬い紫毫を使う。
少しでも時間があれば、筆をとって書いている。
書くという行為は、もはや私にとっては肉体化してしまい、そこにわざとらしさがない。
そうやって、十時間も続けて書いていると、疲れてやめようかと思う頃になって、ようやく良い字が書ける。
疲れてくるということは、雑念がなくなるという事だろうか。
しかし、それが明日につながるという事がない。
一日書き初めれば、いつもふりだしに戻ってどうも気に入らない。
手本は、北魏の墓誌銘、石刻だが、書で生をまっとうできた時代と、こうしてまことしやかに書く時代との果てし無い乖離を考えずにはいられない。
では、何故このように私は書き続けるのか、飽きないでやっていけるのか。
それは、書は簡単に行きつくものではないからであろう。
二十年、こうして続けてきても、なお相手が無限であるとは恐ろしい気もするが、その追いつけないというところに飽きない原因があるのであろう。
白石晟一「書」より
最近のブログ
月別アーカイブ
- 2026年
- 2025年
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (9)
- 2025年10月 (18)
- 2025年9月 (30)
- 2025年8月 (11)
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (7)
- 2025年5月 (69)
- 2025年4月 (41)
- 2025年3月 (10)
- 2025年2月 (17)
- 2025年1月 (27)