買取実績
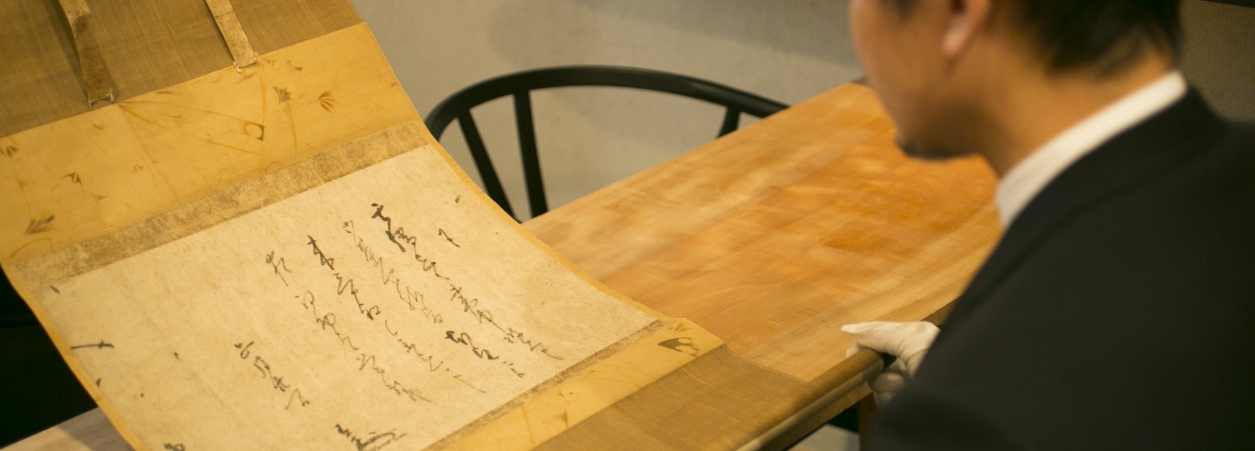
買取実績

工芸品
五節句
蒔絵盃
- 買取地区:
- 犬山市
- 買取方法:
- 出張買取
参考価格¥50,000
蒔絵の盃を買取いたしました。五節句の象徴的な絵柄が描かれています。
五節句は、季節の変わり目に神様にお供え物をしたり、邪気払いをしたりして無病息災を願う年中行事です。
五節句はもともと中国で生まれました。そのため、日付や元々の意味には中国の思想が反映されています。
日本に伝わった時期は定かではありませんが、文献からは奈良時代には日本に伝わっていたと考えられています。
日本伝来後しばらくの間は、宮中や上流階級の貴族の間でのみ行われた年中行事で、たくさんの節句がありました。
五節句は江戸時代になると庶民にも伝わります。江戸幕府が公的な行事・祝日として定めた5つの節句が、日本古来の風習や祭礼と結びつき、人々の間に広まっていきました。
明治6年の改暦の際に五節句の制度は廃止されてしまいましたが、現在でも四季を感じる年中行事として残っています。

五節句の生まれた中国では、奇数を陽の数字(陽数)、偶数を陰の数字(陰数)と考える陰陽思想があります。
奇数同士を足して偶数になるこれらの日は「陽から転じ、陰になりやすい」とされ、邪気を祓うための行事が行われました。
他の五節句は同じ陽数の組み合わせなのに、1月7日の人日の節句だけ異なるのは、1月1日はお正月で特別な日であり、中国の暦でも日本の暦でも別格に扱われたため、1月7日になったといわれています。
現在の新暦になってからは新暦の日付で五節句を行うのが主流ですが、地域によっては旧暦の日付や、月遅れで五節句のお祝いをするそうです。

1月7日 人日の節句(七草の節句)
五節句の始まりである人日(じんじつ)の節句は、前年の厄を祓うとともに、新しい年に無病息災を願う節句です。
人日は文字通り「人の日」という意味があり、人を大切にする(殺したり傷つけたりしない)日と決め、犯罪者を罰さない日としていました。
当日の朝に七草粥を食べる地域が多いことから「七草の節句」とも呼ばれています。
七草粥は冬に不足しがちなビタミンCを補うことができたり、豪華な正月料理で負担がかかった胃を回復させるための食べ物です。また、生命力が高い七草のような植物を食べて、厄祓いをする意味があるともいわれています。

3月3日 上巳の節句(桃の節句)
ひな人形を飾り、女の子の成長を祈る節句とされています。旧暦の3月3日は桃の花が咲く頃であったため、桃の節句とも呼ばれています。
ひな祭りの歴史はとても古く『源氏物語』が書かれた平安時代の頃から様々な家庭で行われてきました。
江戸時代以降に雛人形を飾る「ひな祭り」という日本固有の人形文化となり、現代に受け継がれています。

5月5日 端午の節句(菖蒲の節句)
男の子の成長を祈る節句です。五節句の中で唯一、国民の祝日として休日となっている日でもあります。
端午とは、月の初めにある「午の日」のことで、中国ではその日に菖蒲湯を飲み、厄祓いをしていました。
鎌倉時代以降は、菖蒲が武を重んじる尚武と同じ読みであること、また菖蒲の葉の形が剣を連想させることから、武家の間で祝われるようになりました。
また鯉のぼりには、立身出世を願う意義が込められています。私が子供の頃、男子のいるどこのお宅にも、庭に矢車と大きな鯉のぼりがはためいていました。
中でも覚えているのが、子供の名前が大きく書かれた名前旗が一番上に掲げてあったことです。おそらく個人情報などの問題などから、最近ではすっかり見なくなりましたね。

7月7日 七夕の節句(星祭り)
中国に古くから伝わる牽牛と織女星の伝説から発達した「乞巧奠 (きこうでん)」の行事に、日本古来の「棚機津女 (たなばたつめ)」の信仰が習合したものと考えられています。
奈良時代には7月7日と定められ、牽牛織女の二星を祭るとともに詩歌、縫製、染織などの技術上達を願う行事とされ、江戸時代以降は一般庶民にも広がりました。
古くから笹竹は天の神が降り立つ目印として用いられていたことから、短冊に願い事を書いて笹竹に結び付ける風習が広まっていきました。
「厄災を水に流す」という意味合いから、地域によっては七夕の終わりに笹竹を川へ流したり燃やしたりするそうです。

9月9日 重陽の節句(菊の節句)
中国では「9」の数字は、もっとも大きな「陽」の数とされています。それが2つ重なるこの日は「重陽」と呼ばれるようになりました。
また菊の花を浮かべた酒を飲むと寿命が延びると信じられており、そのことが日本にも伝わり、不老長寿を願う行事となったといわれています。
旧暦の9月9日は、菊が咲く時期でもあるため「菊の節句」とも呼ばれています。この時期には、菊を愛でる菊花展や菊人形展が各地で開催されます。
日本では栗の収穫時期と重なることから「栗の節句」とも言われ、庶民の間では栗ご飯を食べて祝っていました。以前は五節句を締めくくる重要な行事として、盛んにお祝いされていたようです。
近年ではあまり馴染みのない節句もありますが、季節の節目である五節句を取り入れることで、古来の文化を身近に感じることができます。また、家族で季節の移り変わりを楽しんだり、気持ちをリフレッシュすることができるかもしれませんね。
北岡技芳堂では、蒔絵の文箱や硯箱、棗、盃などの工芸品の査定、買取を行っております。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
骨董品の買取につきましては、よろしければこちらもご覧ください。https://gihodo.jp/kotto/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※買取価格は制作年、作風、状態などにより相場が変動いたしますので、
掲載されている金額は、ある程度の目安としてご参考にしていただけますと幸いでございます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
北岡技芳堂では、絵画、掛軸、骨董品、刀剣類などの美術品全般を幅広く取り扱っております。
売却をご検討なさっているお客様や、ご実家のお片付けや相続などでご整理をされているお客様のご相談を承ります。
遺産相続に伴う評価書作成も行っております。
何から始めたらよいのか分からない場合も多いことと存じますので、
ご不明なことなどございましたら、まずはお気軽にご連絡くださいませ。
愛知県、三重県、岐阜県、静岡県を中心に、全国への出張買取も行っております。
【北岡技芳堂 名古屋店】
460-0018
愛知県名古屋市中区門前町2-10
電話:0120-853-860
営業時間:10時〜18時
定休日:日曜(出張が多いため、ご来店の際はご予約をお願いいたします)
#骨董品買取#骨董品#古美術#絵画#版画#茶道具#陶芸品#日本刀#彫刻#金#掛軸#現代アート


